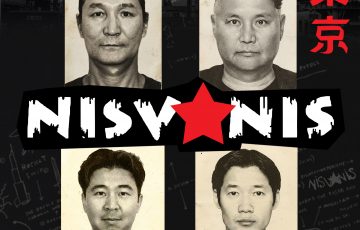<記事の一部を掲載しています>
私が初めてモンゴルを訪れたのは 2000年の夏だった。モンゴル語を学ぶ学校に入った縁で、現地のサマースクールに参加することにしたのだ。
日本を飛びたった飛行機がいよいよ着陸間近というとき、窓から外の景色を眺めたら、視界のすべてが草原と青い空で埋めつくされていた。そこにぽつんと小さな街が1つ浮かんでいて、それが首都のウランバートルだった。今と違って高層ビルもあまり建っていなかった。
当時はひと夏の間、ウランバートル市内にアパートを借りて、近所の語学学校に毎日通っていた。放課後街を歩いていると、知らないモンゴル人から「日本人ですか? 私は日本に興味があるので友達になってください」とたびたび話しかけられた。
というのもその頃、「おしん」や「ラブジェネレーション」といった日本のドラマがモンゴルで放映され、若者を中心に大人気を博していたのだ。さらに日本がモンゴルにとっての最大援助国だということも、親日度が増す理由になっているようだった。
社会主義時代やノモンハン事件のときに敵対視されていたのが嘘のように、日本人というだけで人々が優しくしてくれる。良い思いをすることが多かったけれど、マンホールチルドレンだけは別だった。
日本人とモンゴル人はいくら顔が似ていると言っても、歩き方や服装がまったく違う。だからアパートの外に出ると、私のそばにはマンホールチルドレンがすぐ寄ってきた。
彼らはまず泣きそうな顔をして「お金」と手を差し出してくる。こちらがそれを拒否すると、今度はキッと睨みつけて、地べたにある石を拾い上げては容赦なく投げてくる。逃げるとしつこく追いかけてくるので、一人でいるときは怖かった。そこで自分がなるべく日本人ぽく見えないよう、私はできる限りの大股とガニ股で歩くようにしていた。
モンゴルには一時期、数千人のマンホールチルドレンがいたと言われる。幼い子どもたちは、なぜ暗い地底で暮らさなければならなかったのか?
直接のきっかけは、1990年の社会主義崩壊だった。会社が倒産し、街に失業者があふれ、民衆の生活はひどく困窮した。なかには心が荒れて自分の子どもに暴力をふるってしまう親や、食べさせていけないからと子どもを捨てる親もいたという。
それぞれの事情で家を出ることになった子どもたちは、頼れる大人も存在せず、互いに身を寄せあってマンホールのなかで共同生活を送るようになった。
…………
⬇️全文(残り約1000文字)は月刊望星2019年8月号でご覧ください。
東海教育研究所 http://www.tokaiedu.co.jp/bosei/koudoku.html