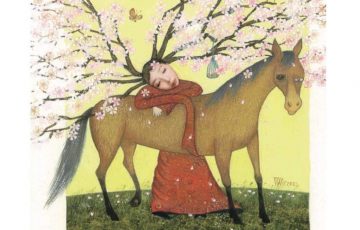11月に開催された「第24回東京フィルメックス」の上映作品ラインナップに、モンゴルからは初参加となる『冬眠さえできれば』(ゾルジャルガル・プレブダシ監督)が選ばれました。そして映画祭終了後、同映画が審査員特別賞と観客賞の2部門を受賞したことがアナウンスされました。この作品は今年5月にカンヌ国際映画祭の「ある視点部門」にもモンゴルから初めてノミネートされて話題になり、今年10月のウランバートル国際映画祭ではゾルジャルガル監督が最優秀監督賞を受賞したばかりです。
東京フィルメックスは、日本の映画祭の中でも本当に力のあるアート系映画しか選ばれない映画祭。2017年にゾルジャルガル監督は『冬眠さえできれば』の企画でこの映画祭の「タレンツ・トーキョー・アワード」を受賞し、初の長編制作に挑む自信を得たと言います。
新モンゴル高校(日本式の教育を取り入れているウランバートルの学校)を卒業し、桜美林大学で映画を学んだゾルジャルガル監督は今回の映画祭に合わせて来日することを望んでいましたが、おめでたいことに直前に2人目の赤ちゃんが誕生! そこでモンゴルから特別にビデオメッセージを寄せ、プロデューサーのバトヒシグさんと母親役を演じた女優のガンチメグさんが映画祭に参加しました。以前監督へ取材したことがきっかけで、この映画の完成を待ち望んでいた私もようやく観ることが叶いました。
ゲル地区の物語
映画の舞台はモンゴルの首都ウランバートル郊外のゲル地区。主人公の高校生ウルジーは、弟と妹と母親と共にゲル暮らしをしています。この家には父親がおらず、母親はアルコールに溺れて仕事に就こうとしないため、生活は常に苦しい状態。長男のウルジーは家事をこなしながら、母親に働くよう説得したり、弟と妹の面倒も見たりと、うんざりして時に逃げ出したくなるような日々を過ごしていました。

「東京フィルメックス」公式サイトより
映画の冒頭で、ウルジーがゲルのかまどで焚く石炭を袋からゴロゴロと音を立てて出すシーンがあり、このいびつな音がゲル地区の生活の様子を生々しく表していました。ウルジー役の俳優さんは本映画がデビュー作で、自身もゲル地区の出身。前作『階段』のときと同様、監督自らオーディションをして選んだそうで、演技は素人でもゲル地区での暮らしぶりが自然なので物語に臨場感を生み出します。

「東京フィルメックス」公式サイトより
大気汚染が問題視される冬のゲル地区(今年のモンゴルも大気汚染がひどいようです)。
夜は人通りが少なく家々の犬の鳴き声ばかりが聴こえるのも、鉄製の重く大きな扉をいちいちドンドンとノックして住人を呼び出すのも、一つ一つのシーンがゲル地区のリアルな光景。15歳までゲル地区で生活していたという監督の強い思いが滲みます。
ウルジーは物理が得意で、学校の先生に見出されて奨学生を目指すようになります。彼に芽生えた希望の光と、それを阻もうとする生活苦という現実の間で、17歳の心は葛藤に揺れます。

「東京フィルメックス」公式サイトより
ある日ウルジーは母親に頼まれ、市内のマンションに暮らす裕福な親戚の家に届け物に行きます(この届け物をする理由もモンゴルならではで面白い)。その家でしばしくつろぎ、せっかくだからお風呂に入って行ったらどうかと親戚の女性に勧められ、遠慮しつつも暖かいお風呂に入ったウルジー。見ているこちらも心和むシーンでしたが……。人間のいやらしさについて考えさせられました。
作品全体を通じて印象に残ったのは、ゲル地区で精一杯生きるウルジー少年の「プライド」です。この「プライド」こそがウルジーを支え、励まし、ある時は大人に歯向かう原因になったのかもしれません。

「東京フィルメックス」公式サイトより
この映画は是枝裕和監督の『誰も知らない』を連想させますが、結末は違います。そしてフィクションではあるものの、限りなくノンフィクションに近い物語だと言えます。

「東京フィルメックス」公式サイトより
ゲル地区の子どもの日常生活の過酷さ、自分たちを惨めな存在にしてはなるものかという若い意地、酒とタバコと音楽、暴力、アルコール中毒の大人、無力な子ども、貧困と寒さ、労働、手を差し伸べてくれる人の存在のありがたさ……。おそらく監督自身が幼い頃から目撃してきた場面がふんだんに盛り込まれているのだと思います。

「東京フィルメックス」公式サイトより
日本での公開予定は?
本作品はモンゴルで2024年1月に公開されることが決まりました。日本では今のところ公開予定が確定していませんが、どこかで上映されることになるはずです。カンヌでは上映後に満員の客席から拍手が鳴り止まなかったそうで、その理由は「モンゴルに限らず、どの国でも共通する物語だから」。
2022年8月に私はモンゴルでゾルジャルガル監督にお会いしたのですが、待ち合わせの場所に彼女がスキンヘッド姿で現れたのでびっくりしました。当時は資金集めに苦労していて、爆発しそうなギリギリの精神状態だったようで「衝動で髪を切ってしまったんです、ハハハ!」と笑顔。監督とプロデューサーのヒシゲーさんは、映画制作を進めながら、並行して数々の現実的なハードルを乗り越え、ついに完成までこぎつけました。現代モンゴルの社会問題を、映画という手段で観客を惹き込みながら表現し、深刻な物語のなかにもどこか明るさと希望を混ぜ込むところがゾロジャルガル監督の真骨頂です。